|
2024年5月16日
近年の「腸活」や「菌活」ブームにより、自分の腸に関心を持ち、腸に良いとされる食を積極的に選択する人が増えてきました。私たちの腸の中には、およそ1000種類、40兆個とも見積もられる細菌(腸内細菌)が棲んでいます。この腸内細菌の群集のことを腸内細菌叢(腸内フローラ)と言います。この腸内フローラを四半世紀にわたって研究してきたのが、慶應義塾大学先端生命科学研究所 福田 真嗣 特任教授です。アジレントの質量分析計を研究に活用されている福田特任教授に、腸内フローラの研究や、その研究成果の社会実装についてお伺いしました。福田特任教授のチームによる最近の研究成果「短鎖脂肪酸と胆汁酸の同時定量法の分析メソッド開発」においては、アジレントのアプリケーションエンジニアも継続的にサポートを続けてきました。
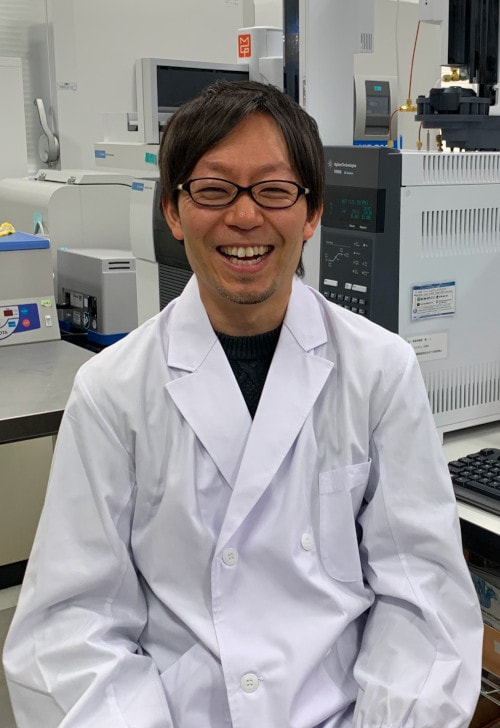
慶應義塾大学 先端生命科学研究所 福田 真嗣 特任教授
「もう1つの臓器®」:腸内フローラの謎を解き明かす
昨今、様々な領域の研究者が腸内フローラの研究に取り組んでいます。腸内フローラの研究が盛んになっているのはなぜでしょうか。腸内フローラは、胃や小腸で消化・吸収されなかった未消化物をエサにして化合物(代謝物質)を作り出します。その代謝物質は、血液を通じて全身をめぐることになります。腸内フローラは、代謝物質を作り全身に送り出す機能を持った、いわば「もう1つの臓器®」と捉えることもできます。腸内フローラとそれが作り出した代謝物質が、免疫、代謝、脳など、ヒトの体の様々な機能に影響を及ぼすことが解き明かされるにつれ、ゲノム、免疫、代謝、脳、バイオインフォマティクス などの異分野の研究者もますます腸内フローラ研究に関心を示すようになっています。腸内フローラ研究を推進することで「もう1つの臓器®」の機能解明が進めば、その研究成果は私たちの「生活の質」、「生命の質」、「人生の質」 (Quality of life) に貢献することになります。腸内フローラの正しい理解とコントロールが、健康維持や病気の予防・治療につながることが徐々に明らかになってきています。
腸内フローラが作り出す代謝物質のなかには、酢酸、プロピオン酸、酪酸といった、短鎖脂肪酸と呼ばれる化合物があります。短鎖脂肪酸は私たちの健康に大きく貢献することが様々な研究により明らかになっていることから、ヘルスケア領域においても注目を集めています。福田特任教授自身も、2011年、ビフィズス菌が作る酢酸が腸管上皮細胞に作用して腸管出血性大腸菌O157:H7による腸管感染症を抑制するという研究成果をnature誌に発表し、2013年には腸内細菌が作る酪酸がアレルギーなどを抑える役割を担う制御性T細胞の分化誘導を促進することを明らかにし、この研究成果もnature誌に報告しました。このように短鎖脂肪酸の有用性を次々と明らかにしてきました。
腸内フローラ研究の発展を支えた技術とは
短鎖脂肪酸を含む腸内環境について大学生の頃から四半世紀にわたり研究を続けている福田特任教授は、学生時代と最近の研究の違いをこう話します。
「データ駆動型のオミクス研究が可能になる前は、注目した遺伝子/タンパク質/代謝物質についてのみ評価を行う仮説検証型の研究が主流でした。そのため『良い影響を及ぼしているのは短鎖脂肪酸ではなく、分析されていない他の物質の可能性はないのか?』と聞かれても、明確に回答することはできませんでした。しかし、2000年代以降の技術革新により可能になったオミクス研究では、網羅的な解析を実施することで、結果として他の物質ではなく短鎖脂肪酸が確実に重要であることを証明できるようになりました。」
福田特任教授の話す「研究の違い」をもたらした網羅的解析は、分析装置とコンピューターサイエンスの進展があったからこそ実現できたものだと言えます。腸内フローラ研究の領域では、2000年代中盤までに、次世代シーケンサー (NGS) により腸内に存在する細菌の遺伝子を網羅的に調べる「メタゲノム解析」と、核磁気共鳴装置 (NMR) や質量分析計を用いて腸内細菌によって作り出された代謝物質を網羅的に調べる「メタボローム解析」が、本格的に活用されるようになりました。網羅的解析により得られた大量のデータを処理するバイオインフォマティクスの発展も研究に大きく貢献しました。
メタボローム解析において、福田特任教授は、サンプルを非侵襲で分析でき短時間でも測定結果が得られるNMRと、比較的高感度な分析が可能な質量分析計とを目的に応じて使い分けています。さらに、質量分析計は、揮発性化合物の分析に向いているガスクロマトグラフ質量分析計 (GC/MS)、中性物質や脂質の分析に適した液体クロマトグラフ質量分析計 (LC/MS)、イオン性化合物の分離に優れたキャピラリー電気泳動質量分析計 (CE/MS) があり、慶應義塾大学 先端生命科学研究所にはアジレント・テクノロジーの質量分析計が多数導入されています。福田特任教授も、これらの質量分析計を目的に応じて使い分けながらメタボローム解析を行っています。

アジレント・テクノロジーの質量分析計が多数導入されている慶應義塾大学 先端生命科学研究所(写真提供:慶應義塾大学)
病気ゼロ社会の実現を目指した取り組み
福田特任教授は大学で腸内環境研究を進めるとともに、2015年に自ら立ち上げた株式会社メタジェンの代表取締役社長CEO(最高経営責任者)を務めています。なぜ研究者と経営者の二足の草鞋を履くのでしょうか。サイエンスは人類のためにあると考える福田特任教授は、研究成果を社会実装することも自身の役割だと考えているからです。そこで、大学で腸内環境研究を続けつつ、メタジェンでその研究成果をシームレスに社会実装することで、同社のグループビジョンである「病気ゼロ社会」の実現を目指しています。
病気ゼロ社会を実現するには、病気の人を治す「治療」と、日頃から健康を維持する「予防」の2つのアプローチが必要です。予防という観点で、メタジェンでは、個人の腸内フローラのパターンにあったヘルスケアを実現する「層別化ヘルスケア」、さらには求める方向に腸内環境を制御する「腸内デザイン®」を推進しています。この実現にあたっては、自分の腸内にどんな細菌が棲んでいるのかを見て(見る)、腸内で何が起きており、自分にとって最適なアプローチを知り(知る)、病気につながる細菌を減らしたり、ヒトにとって有用な細菌を増やしたりする(操る)必要があります。
自分の腸内にどんな細菌が棲んでいるのかは、便をサンプルとする腸内フローラ検査で調べることができます。便は健康に関する情報が詰まった「茶色い宝石®」とも言えます。しかし、自分の腸内にどんな細菌が棲んでいるのかを知っている人はまだ多くはありません。現状、自分の腸内フローラのパターンを知っている日本人は全人口の0.1 %程度と見積もられています。「自分の血液型を知っている人の数と比べたら、自分の腸内フローラのパターンを知っている人の数は圧倒的に少ない」と、福田特任教授は言います。しかし、自分の腸内フローラを知ることを文化として定着させるべく、着実に歩みを進めています。その一例が、メタジェン、食品メーカー、腸内フローラ検査を手掛ける企業の3社が連携して開発した、個人の腸内フローラを検査し、個人の腸内フローラにあわせたグラノーラを定期購買するサービスです。個人の腸内フローラを知ったうえで、その腸内細菌が利用しやすい成分をグラノーラとして摂取します。
「腸内フローラは人によって違うので、同じものを食べても全員に同じ効果があるとは限りません。」
かねてからこのように主張してきた福田特任教授。腸内フローラを知っているのが当たり前の世界では「一般に腸に良いと言われているもの」ではなく、「科学的に私の腸に適したもの」を摂ることができるようになるわけです。構想から8年、「腸内デザイン®」の一歩手前の「層別化ヘルスケア」は身近なものになってきました。
病気ゼロ社会に向けた研究環境づくり
メタジェンでは2115年までに病気ゼロ社会を実現するというロードマップを持っていますが、その実現のためにはもっと多くの研究者が腸内フローラの研究を進め、より多くの研究成果が発表される必要があります。腸内フローラ研究分野には、遺伝子、免疫、代謝、脳、バイオインフォマティクスなど、様々な分野の研究者が参入していますが、福田特任教授は、便のメタボローム解析は研究領域として十分に広まりきっていないと感じており、その理由の1つが標準的な分析技術・装置が確立していないことにあると考えていました。腸内フローラのメタゲノム解析はNGSが普及していることもあり、世界中で盛んに行われています。一方、「メタボローム解析」では分析機器のメーカーが変わると分析結果が変わったり、同じ装置でも結果がばらついたりすることがあると言います。
これまで福田特任教授は、便中に含まれる腸内フローラ由来の機能性代謝物質の同定には一般的なメソッドを使ってきました。たとえば、CE/MSで使っていたメソッドは、細胞、組織、血液中の成分を分析するのに適したものでした。一方、研究が進むにつれ、便中に含まれる機能性代謝物質に関する知見が蓄積されてきました。短鎖脂肪酸や胆汁酸、アミノ酸代謝物質がその例です。腸内フローラから作られるこういった機能性代謝物質を分析するのに最適化された技術を開発したらよいのではないかと考えました。
福田特任教授のところには、日本中の研究者から、そして時には世界各国の研究者からも便が集まってきます。便中に含まれる機能性代謝物質の知見が蓄積されており、多くのサンプルが集まる福田特任教授のチームが便中の代謝物質に特化した分析方法を開発するというのは、自然な流れでした。
メソッド開発にあたって使用した分析装置はアジレント製のGC/MSでした。揮発性の高い短鎖脂肪酸はGC/MSで分析しますが、胆汁酸はLC/MSで分析するのが一般的です。目的に応じて質量分析計を使い分けているはずの福田特任教授が、なぜGC/MS のみで短鎖脂肪酸と胆汁酸を分析しようと考えたのでしょうか。それは、多くの研究機関や大学がシングル四重極GC/MSを持っており、GC/MSをベースにすれば、設備投資のハードルが下がると考えたからです。これにより、便のメタボローム解析を行う研究者が増加し、多岐にわたる知見が蓄積されていくことを期待しています。知見が増えるほど、それだけ人類は恩恵を受けることができ、病気ゼロ社会の実現に近づきます。
福田特任教授はこう続けます。
「私は腸内細菌の専門家ですが、分析化学の専門家ではありません。おそらく分析化学の専門家であれば、『短鎖脂肪酸と胆汁酸を同じ装置で分析したい』とは言わないと思います。その分野の常識を知らないということは強みでもあります。私の場合、分析化学の専門家ほど詳しくは知らないからこそ、臆せずに、『短鎖脂肪酸と胆汁酸を同じ装置で測れませんか?』と言えたのだと思いますし、腸内細菌の研究にはそれが必要なんだろう、と周囲のメンバーに捉えてもらえたことで、実現に向けた議論がスタートしました。」
この分析メソッドを開発できたのは福田特任教授とそのチームメンバーの努力の賜物ですが、その裏にはアジレントのバックアップがありました。

GC/MSをベースに短鎖脂肪酸と胆汁酸の同時定量法を開発(写真はAgilent 5977B GC/MS)
福田特任教授のメタボローム研究を後押しするアジレント
福田特任教授は、メタボローム研究を進めるにあたって、アジレントのサポートは欠かせないと言います。
「アジレントとの出会いが私のメタボローム研究を後押ししているのは間違いありません。短鎖脂肪酸と胆汁酸の同時定量法の分析メソッド開発においても、アジレントのアプリケーションエンジニアには数年にわたってずっとサポートしてもらいました。短鎖脂肪酸と胆汁酸を同時に測るというのは大きなチャレンジでしたが、メタボローム研究者の先生方と腸内環境研究者の私、そして質量分析の専門家のアジレントのエンジニアのサポートがあって初めて実現できたことだと思います」
また、アジレントのアフターサポートも役立っていると言います。
「便のメタボローム解析を行うと、質量分析計が汚れるため、メンテナンスにも気を遣う必要がありますが、(慶應義塾大学 先端生命研究所や株式会社メタジェンの本社のある)山形県鶴岡市では何か問題があればすぐにアジレントのサービスエンジニアに対応してもらえます。私自身は質量分析計の専門家ではないので、トラブルがあると困ります。困ったときに相談できる相手がすぐ近くにいるというのは安心感につながりますし、非常に助かります。今後新たに装置導入を検討する場合、アフターケアまで含めたトータルサポートで判断すると思います。」
「研究成果を社会実装する」「研究成果を社会に発信する」―――これは、福田特任教授が何度も繰り返した言葉です。アジレントも同じ考え方を共有しており、 “Let’s bring great science to life” (科学の叡智を、生活と生命へ)というメッセージを発しています。アジレントでは、科学の叡智を社会に展開できるよう、一丸となってお客様をサポートしています。
ウェルビーイングに資する腸内デザイン®
福田特任教授は、「将来的には、各個人が求める機能にあわせて腸内環境を変えていくようなサービスを社会実装したい」と、未来像を示しています。一人ひとりが想い描く理想状態、いわゆるウェルビーイングに資する腸内環境の研究開発を進め、腸内デザイン®で人間の機能向上を実現するサービスを実装したいと言います。医療はマイナスをゼロに戻し、ヘルスケアは現状維持であるのに対し、ウェルビーイングは、さらに積極的に機能を高めていくというコンセプトです。
将来的にはどのような機能を向上させることができるようになるのでしょうか。一例として、福田特任教授のグループが2023年にScience Advances誌に発表した研究にそのヒントがあります。福田特任教授は「大学駅伝強豪校の強さの秘訣は腸内細菌にある」という仮説を立てて、青山学院大学の長距離ランナーの腸内フローラを分析しました。その結果、ヒトの主要な腸内細菌の1つであるBacteroides uniformisが腸内で短鎖脂肪酸を産生することで持久力を向上させること、さらにはB. uniformisが栄養源として利用しやすい環状オリゴ糖を摂取することで、一般の方の持久力も向上できることを臨床試験で証明しました。メタゲノム解析とメタボローム解析を組み合わせたメタボロゲノミクス®を基盤とした腸内環境研究を四半世紀行うなかで、未だなお短鎖脂肪酸の新たな機能が見つかるのは、本研究分野が未開の地であることの裏付けでしょう。
福田特任教授は、「腸内デザイン®で一人ひとりの想いを叶えるために、まずは自分の腸内フローラを知ることが当たり前になる文化を形成したい」と、未来の姿を語っています。
この記事に掲載の製品はすべて試験研究用です。診断目的には利用できません。
DE49790088 |